|
|

ボウリングボール 100年の進化を辿る
(2016年10月号 日坂義人の今すぐ役立つ 実践ボール講座 特別編より)
数種類のボールを操ることが当然になった現在のボウリングですが、1983年以前には、
ゲーム中にボールをチェンジすることが禁じられてきたことをご存知でしょうか。
日本に民間のボウリング場が開場したのが1952年ですがから、それ以前のボールとなると、
残されてる書物でしか確かな情報を得ることができません。
今月の実践ボール講座特別編では、第1次ボウリングブームからのボールの進化の変貌を辿り、
ボールの技術革新の歴史を振り返ってみたいと思います。
長期に渡るラバーボール時代(1905〜1970)
1905年、米国で初のラバーボールが誕生しました。
それ以前は、癒そう木(ゆそうぼく)という、船のスクリューの軸受けなどに
使われていた木製のボールが投げられていましたが、欠けたり、傷つきやすいという問題があり、
それに代わってハードラバーボールが製造されるようになったのです。
同時にこの年、ABC(米国ボウリング協会=現在のUSBC)が、それまでまちまちだったボールの
重量を16ポンド以下に制限。以来、現在に至るまで、ボールの重量にはその規制が通用されています。
その後、日本に上陸した1960年代から、ボウリング第1次ブームを支えた70年代まで続いたのですから、
ラバーボール時代は長期に渡り、ボウリングボールの主役だったことに間違いありません。
当時、ボールの表面は硬い方が反発力があるといわれ、表面硬度が90度というボールまで製造されました。
その頃のデーターを見ると、ボールの表面硬度の平均は85度前後で、現在では硬めの領域ですが、
当時は平均な硬度として、各ボールメーカーが設定していました。
反発力以外のもう1つの理由として、レーン表面のコーティング材がラッカー系塗料だったために
表面が柔らかく、コンディショナーオイルがなくなると、どうにもならないくらい曲がってしまい、
走りを優先するボールが求められたのです。
1972年頃のラバーボールは、断面の写真にあるように、コア部分はコルク質で、
上部に重いウェイトブロックが埋め込まれている構造でした。
今のようにRG(回転半径)といる概念がなかったために、重いボールの方が中心部分の比重が高く、
転がりやすかったのです。

(参考画像 日坂語録より引用)
ボール表面を軟化させる時代へ(1970〜1975)
70年代に入り、新たな技術革新が起こりました。米国のPBAプレーヤー、ダン・マキューンがラバーボールを
MKN=(メチル・エチル・ケトン=軟化薬)という溶剤に漬け、表面を軟化させたボールで試合に臨んだところ、
当時の記録をことごとく塗り替えてしまったのです。
ボールの表面を軟らかくすることにより、衝撃の吸収力を高める効果が発見され、
一時流行となったのですが、MEKが
劇薬であり、火災の原因にもなったことから、1973年には軟化薬に漬けるソークボールが
ルールで禁止される事態にへと発展しました。
その時点からボールメーカーは、表面硬度を低く設定するように、180度方向転換することになりました。
当時のボールは、表面に爪を立てると、その凹み跡が残るほど軟らかかったことが思い出されます。
しかし、軟らかすぎるボールはマシントラブルを起こすこともあり、ABCは表面硬度を規制。
「Dスケール72度」以上という製造上の規定を新たにルール化し、その規制が現在まで継続しています。
この時点では、表面素材はまだソフトラバーやソフトプラスチックでしたが、
水面下ではウレタン素材が研究され始めていたようです。
ウレタンボールの開発(1980〜)
70年代後半になると、レーン表面のコーティング材が、ラッカーからウレタンへと移行し始めます。
ラッカーは引火点が低く、火災の原因となったこともあり、堅牢で火災の起きにくい
ウレタン塗料が開発されたのです。
ウレタンのレーンコーティングは、表面が滑らかで滑りやすく、
ソフトラバーやソフトプラスチックをもってしても曲がりが出にくかったのです。
それに比して、ウレタンボールはラバーやポリエステルより摩擦係数が高いため滑りにくく、
ウレタン同士が接触することでさらに摩擦力が高まるため、当然フックポテンシャルが
高くなる特性が発見されたのです。
そのウレタンボール第1号として1981年に誕生したのが米国AMF社「アングル」でした。

(参考画像、ウレタンボール第1号として誕生したアングル)
2ピースセンターヘビーコアの誕生(1984〜)
遅れて2年後の1983年には、国産のウレタンボール「センチュリー」が誕生しますが、
この時点ではまだボールの構造的な変化はなく、
パンケーキ型のウェイトブロックが採用されていました。
所が翌年84年、突如として米国から上陸してきたのが2ピース(2層)構造の「ハンマー」です。

(参考画像 日坂語録より引用)
なぜ2ピース構造なのか、
その時点では見当もつきませんでしたが、これが力学的発想の先駆けだったのです。
ボールの中心部分を重くすることは、慣性モーメント(転がりの指数)を低くするために
ボールの転がりが増えることになり、
フックポテンシャルにも影響を及ぼすことになるのですが、動的バランスが理解されてない
この時代には、単にスタティックバランス(静的バランス)の
レイアウトでしか、手法がなかったのです。
高摩擦リアクティブレンジの幕開け(1990〜)
「リアクティブレジン」という表面素材は、今でこそ高摩擦ポリウレタンカバーの代名詞として
日常的に使われるようになりましたが、当時は「タッキーシェル」とか「ウエットウレタン」というのが、
これらの表面素材でした。
素材の感触に、しっとりとしたウェット感があったことでそう呼ばれたのですが、
この新素材が新たなリアクティブ特性を生み出しました。
オイル上では摩擦力が低下し、ドライゾーン移行時には本来の摩擦力に戻るため、
かつてないアグレッシブな動きと入射角をもたらしたのです。
ウレタンに可塑剤を添加したことで、これらの現象が発見されたのですが、
以来、リアクティブの呼称は現在に至るまで長きに渡り、
カバーストックの主役を保つことになったのです。
高摩擦のパーティクルの参画(1991〜)
90年代に入ると、レーン上のオイルがさらに多く散布されるとうになり、
同時にそれまでのウッドレーンに代わり、シンセティック(合成)レーンが普及し始めました。
ウッドレーンに比べ、表面硬度が硬くなるとともに、レーン上の摩擦が低下するようになったのです。
そうなると、リアクティブカバーはオイルに左右されやすくなり、オイルの変化によって
リアクションも不安定になってきます。
その対策として、新たに開発されたのが、リアクティブに新たな固形添加物を混入した
パーティクルカバーでした。
パーティクルカバーは摩擦力が高く、オイル上での安定感に優れた素材でした。しかし、
手前からのオイルキャッチ感が強いということは、
反面、ボール軌道が緩やかになり、シャープな曲がりを求めるタイプににとっては不満が残り、
パーティクルの固形物も寿命が短く、リアクション低下も早まるなど、その人気は長く続きませんでした。
ダイナミックバランスによる新たなドリル理論(1994〜)
2ピースボールの物理的効果が明らかにされないまま、米国ボールメーカー数社では、
パンケーキ型ウェイトブロックと
2ピースセンターヘビーコアが混在しながらボール製造が推移していました。
そんな中、1992年には、米国ブランズウィック社が
ついにコアの比重を変えた慣性モーメントの物理概念をボール設計に採用。
同時にコアのレイアウトにより、リアクション
(フレア調整)を調整するダイナミックバランス(動的バランス)を新たにドリル理論として提唱、
回転軸にコアをどうレイアウトするかという画期的なドリル手法を明らかにしたのです。
PAP(ポジティブ・アクシス・ポイント)の重要性はここで教示され、
それを機に米国各メーカーは発売ボール個々にドリルインストラクションを添付、
PAPを基準にしたレイアウト手法が新たな理論としてスタートしたのです。
コアデザインの進化(1995〜)
動的バランスを利用したレイアウトの理解が浸透してくると、
メーカー各社は様々なコア形状をデザインするとうになりました。
コアの形状だけでなく、比重を変えることも巧みに応用され、カバーストックの摩擦力とのマッチングにより、
軌道を変えるアイデアまで盛り込まれるようになります。
センターヘビーはオイリー用、カバーヘビーはドライコンディション用と、
コア設計に慣性モーメントが導入されると、ABCはすかさず
ボールの製造上の規定の中に、RG(回転半径)ΔRG(回転半径差)という
慣性モーメントにおける物理量を規制し、ルール化しました。
つまり、用具が身体能力を超えるべきではない、というスポーツとしての歯止めをかけたのです。
しかし、高性能ボールの出現はストライクを増産し、
さらなるハイアベレージ時代へと突入していく結果となりました。

(参考画像 日坂語録より引用)
マスバイアス効果と非対称コアの誕生(1998〜)
やがてレーン上のボールモーションの解明が進み、
コアの動力がボールモーションに反映される時代へと移行して行きます。
米国ボールデザイナーのモー・ピネル氏が提唱した「マスバイアス理論」による、
PAPの軸移動を応用したリアクション調整を
コアのレイアウトで微調整するという手法が広まり、
ボールメーカーは非対称コアを製造し始めるようになります。

そうなると、ますます新たなドリルスキルが求められるようになり、
動的バランスを利用したレイアウトテクニックを学ぶことがドリラーには必須となりました。
エポキシ樹脂が新素材として登場?(2000〜)
コアの進化と同時に、カバーストックはさらに摩擦力増強の時代へと移行していきます。
パーティクルの種類も、カーバイトやマイカ(雲母)ガラスバルーンと、様々な添加物が研究されましたが、
なかなかリアクションの早期低下を解消するには至りませんでした。
そのような状況下、突如それらに代わる表面素材として、エポキシ樹脂が登場しました。
エポキシ樹脂のボールはオイル吸収力が際立っていましたが、
吸収が早すぎてリアクションが低下するなど、新素材とはいえ、
これも問題が多すぎて話題の提供にどとまり、大きな普及には至りませんでした。
ケミカルフリクション時代の到来(2006〜)
カバー素材のさらなる開発は進み、米国エボナイト社はついに、
それまで物理的摩擦(サンディング・ポリッシュ)に代わり、
オイルを吸収することで摩擦力を保持するマイクロテクスチャーを開発、
カバーストックの大きな転換期がやってきました。
化学合成によるミクロ粒子の表面を形成するケミカルフリクション(科学的摩擦)技術が開発されたのです。
米国各メーカーはこの技術に着目、カバーストックは化学合成による表面粒子形成の方向へと、
新たなイノベーションの転換を
強いられ、以後、様々な進化の中で現在に至ってます。
★
この半世紀におけるボールの進化は著しいものがあり、スポーツの用具として、
人間本来の身体能力を超えてはいけないという前提のもと。
ABC改めUSBCにおいて様々な規制が打ち出されているのが現況です。
果たしてボウリングボールは今後どのような進化を遂げるのか、注目されるところです。
|
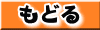
|
|
|

